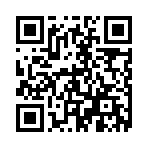2006年06月13日
江戸の絵具
絵を描くとき、布や紙を染めるとき、「色材」に何を使うか。
これは、ここ数年のコトリのテーマの一つです。
最近では、土や植物の色で染めたり、絵を描いたりと、天然の材料が気になっています。
そんな折、東京の板橋美術館で「江戸の小粋~色のパレット~」という講演会に参加してきました。板橋美術館では「江戸狩野派」の展示中ですが、さてあの日本画の色は何で描かれているのか?というのがテーマです。
化学の絵具がなかったこの時代、人々は、自然界にあるものから色をもらっていました。鉱物系・動物系・植物系。紅型で使われる顔料も、主に鉱物から作られているようです。
「今、塗っている色は、赤鉄鉱からできているんだ」とか「この青色は、藍銅鉱の色」とか「この土は何億年前から堆積したものなのね」なんて認識しながら色を塗るのは、わくわくしますし、想像の世界がふくらみます。
実は「日本画」というものに、今まで興味がありませんでした。
鶴とか亀とか、金色の屏風とか、そういうイメージが先行し、それ以上深く近づいていこうという気持ちがもてなかったのです。でも、西洋画と日本画の違いは、描くものではなくて色材の違いだということを知り、今さらですが「日本画」に憧れています。現代でも天然の絵具をたくさん使っているのは、世界的にみても日本画くらいだといいますから。
世界を歩いて、カラフルな色の土を集めて絵を描きたいです。
まずは沖縄から探索です。
これは、ここ数年のコトリのテーマの一つです。
最近では、土や植物の色で染めたり、絵を描いたりと、天然の材料が気になっています。
そんな折、東京の板橋美術館で「江戸の小粋~色のパレット~」という講演会に参加してきました。板橋美術館では「江戸狩野派」の展示中ですが、さてあの日本画の色は何で描かれているのか?というのがテーマです。
化学の絵具がなかったこの時代、人々は、自然界にあるものから色をもらっていました。鉱物系・動物系・植物系。紅型で使われる顔料も、主に鉱物から作られているようです。
「今、塗っている色は、赤鉄鉱からできているんだ」とか「この青色は、藍銅鉱の色」とか「この土は何億年前から堆積したものなのね」なんて認識しながら色を塗るのは、わくわくしますし、想像の世界がふくらみます。
実は「日本画」というものに、今まで興味がありませんでした。
鶴とか亀とか、金色の屏風とか、そういうイメージが先行し、それ以上深く近づいていこうという気持ちがもてなかったのです。でも、西洋画と日本画の違いは、描くものではなくて色材の違いだということを知り、今さらですが「日本画」に憧れています。現代でも天然の絵具をたくさん使っているのは、世界的にみても日本画くらいだといいますから。
世界を歩いて、カラフルな色の土を集めて絵を描きたいです。
まずは沖縄から探索です。
Posted by コトリ at 00:23│Comments(4)
│本・映画・アート
この記事へのコメント
いつもいつも探究心旺盛なコトリちゃん。
きっといい作品が生まれるでしょうね。
しかし、絵心のない私は初めて聞く話で面白かったです。
きっといい作品が生まれるでしょうね。
しかし、絵心のない私は初めて聞く話で面白かったです。
Posted by Romi at 2006年06月13日 16:11
私も天然の色が大好き。
同じく、世界中の土顔料を集めたいとひそかに思い続けているけど、
忘れちゃうのよねぇ~土採取。
まずは身近な場所の土から始めて行こうかな。
沖縄は雨がすごそうだけど、
気をつけて帰ってね。
再会を楽しみにしています。
同じく、世界中の土顔料を集めたいとひそかに思い続けているけど、
忘れちゃうのよねぇ~土採取。
まずは身近な場所の土から始めて行こうかな。
沖縄は雨がすごそうだけど、
気をつけて帰ってね。
再会を楽しみにしています。
Posted by 亜 at 2006年06月13日 23:24
Romiさん>最初は、ただ絵を描くことが楽しかったのですが、色材のことなど理論的に勉強するのも新鮮で楽しいのです。
もしも、色材作りからはじめるとすると、絵本をつくるまでにずい分と歳月がかかりそうですが、じっくりゆっくりやっていきたいです。
もしも、色材作りからはじめるとすると、絵本をつくるまでにずい分と歳月がかかりそうですが、じっくりゆっくりやっていきたいです。
Posted by コトリ at 2006年06月14日 00:20
亜さん>アラスカの土、一握りもってかえってきて!!(でも、土重いんだよね)一緒に「世界の土コレクター」になりましょう。つねにスコップとビニール袋を持参で(笑)
雨の沖縄気をつけて帰ります!
雨の沖縄気をつけて帰ります!
Posted by コトリ at 2006年06月14日 11:24